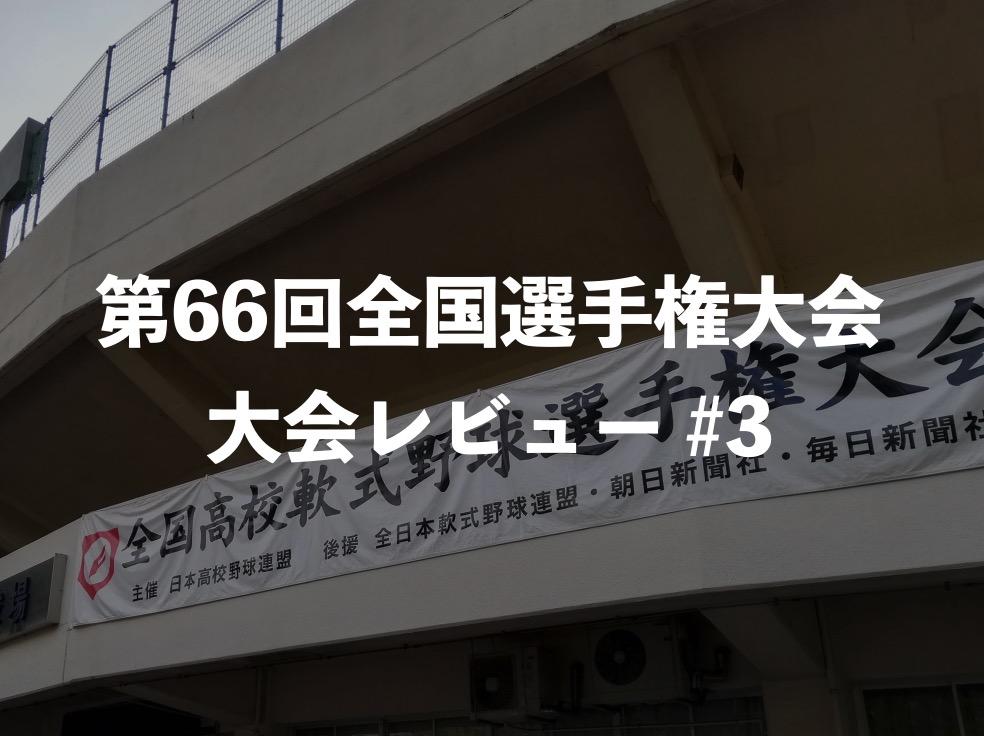2年ぶりに開催された高校軟式野球の全国大会「第66回全国高校軟式野球選手権大会」は、北関東代表の作新学院が6年ぶり10回目の優勝を果たして、軟式界の王座に返り咲いた。
今大会を筆者の視点で、全4回に渡って振り返る。
軟式の全国大会で初の500球制限が導入
今大会は「500球制限」が導入されてから初めての全国選手権大会だった。結果、大会を通して500球に到達した選手はいなかった。
今大会、最も多くのイニングを投げたのは、優勝した作新学院のエース・小林で421球だった。準決勝の浜田戦で4点リードの8回に福島にマウンドを譲った(22球)が、その試合を投げ抜いていたとしても、制限に対しては余裕があった。
現状の軟式の全国選手権大会は休養日を含めて6日間で行われている。そのため大会を通して1人の投手が投げられる球数が500球ということになる。
この「500球」の根拠や是非については様々なところで議論されているので、そちらに任せたい。ただ事実として、「500球」は軟式で全国制覇をするチームのエースであれば、1人でも十分投げ切れる基準であることは否めない。
(正直、今大会の作新学院の準決勝の継投も、ゲーム展開的な必要性はそこまで高くなかった。)
【近年の決勝進出チームの球数】
| 第66回 (2021) |
作新学院・小林 | 421球/34イニング |
| 中京・内野慎 | 315球/23イニング | |
| 第64回 (2019) |
中京・水 | 457球/35イニング |
| 崇徳・高井 | 436球/29・2/3イニング | |
| 第63回 (2018) |
中京・佐伯 | 480球/36イニング |
| 河南・山岸 | 508球/35イニング |
確かに今大会の完投は11ケースで、第64回大会の19から大幅に減少している。500球制限によって、各チームに継投の意識が広がったことは明らかだ。
ちなみに500球制限は現在は試行期間中で、2023年度から正式に決定される。
過密日程という根本的な問題は手つかずのまま
500球制限以前の問題として、軟式は決勝まで進んだ場合、6日間で4試合を消化しなければいけない。
第61回大会(2016)から準々決勝翌日に休養日が設けられるようになったが、それ以前は5日間で4試合という超過密日程だった。1回戦が大会2日目のチームは、決勝まで4日連戦という、前時代的にもほどがあるスケジュールが、つい最近まで組まれていた。
硬式は今年の夏から、休養日を1日増やしたことで完全に連戦が解消された。
一方、同じ連盟下の高校生が行う軟式野球では、連戦が残り、しかも超がつく過密日程で行われている。
「硬式の方が球が重く、投手の負担が大きいから」なのだろうか。百歩譲ってそうだとしても、野手に関しては1試合の疲労度に大きな差があるとは思えない。
滞在期間が伸びることで参加校の経済的な負担が増える(補助を出している連盟の負担も、もちろん増える)、練習会場の確保が難しいなどの課題があることも承知している。
しかし後回しにされ続けてきた根本的な問題について、手を付けざるを得ないときに来ているのは、誰の目から見ても明らかだ。
ことしの夏に浮き彫りになった甲子園の日程の議論と合わせて、高校野球、いや学生スポーツ全体で検討されなければいけない喫緊の課題と言える。